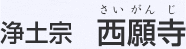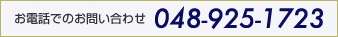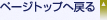右は仏 左は私 合わす掌 10月
When you bring your hands together in prayer, you bring the Buddha and yourself together.
今年のゴールデンウイークに小学校の同級生から連絡が入りました。コロナが落ち着いたので、6年生の時に埋めたタイムカプセルを掘り起こすという内容でした。
有志で掘り起こし、そこから同級生のもとへ届けるということで、私のところに届いたのは6月の終わり。入っていた当時の手紙を見ると、乱筆でしたが、内容は素直にその時の想いを書き残していました。
今はこの素直な気持ちを忘れ、年を重ねるなかで、色々なことを疑いの目で見たり、人の揚げ足を取ったり、さまざまな環境に流されている自分を痛感しました。自分の手紙を見て、物事と真っすぐ向き合うことの大切さを過去の私に学びました。
皆さまも幼い時は、言われたことを疑わず真っすぐ信じていたのに、大人になり、どこか疑いの心を持ってしまうことがあるのではないでしょうか。
物事に真っすぐ向き合うということは、日々皆さまが本堂、お墓、お仏壇でお参りする時にも大切なことです。
合掌してお参りをする皆さまの西方極楽浄土への往生の願い、亡き大切な方を思い浮かべ、お浄土で再会を果たしたいという気持ち、またご先祖さまへの追善の回向や供養。これは本当にありがたく尊いものです。しかし、合掌をしていても暑いなあ、お腹すいたなあと、余計なことが頭をよぎり、そういった想いと真っすぐ向き合えていないことはありませんか。
今月の標語は、仏さま、ご先祖さまなどに尊敬・感謝の気持ちを捧げる際に自然と行う「合掌」を表しています。
合掌は、右手が阿弥陀さま、左手が日々迷いの世界を生きる私たちを指します。この二つの手が合わさることにより、仏さまと私たちが真っすぐと向き合い、阿弥陀さまを信じて疑わないということを意味するとも言われます。
合掌の意味を意識しながら手を合わせることで、自然と心が阿弥陀さまや大切な方に向き、さらに、お念仏をとなえることで、その方々に想いを伝えることが出来るのではないでしょうか。
西方極楽浄土にいらっしゃる亡き大切な方は、皆さまのお参りの姿を見守り、お念仏の声をお聞きになってくださいます。そのことに喜びを感じ、手を合わせ、お念仏を一心におとなえいたしましょう。
(神奈川県横浜市 大光院 宮林成彦)
備えは今から 9月
The time to get ready is now.
「泣いていいんだよ」という歌い出しで始まる菅田将暉さんの『虹』という楽曲があります。私の知人に、サビの部分で「一生そばにいるから 一生そばにいて」と歌う彼の声に涙する方がいます。
大切な人を亡くしたらいろいろな反応が出ます。悲しみや後悔、自責の念、眠れない、孤独感、「なぜ」という問いなど、どれも自然な反応ですし、人によって反応の出方は違います。自分のなかでも時と場合によりさまざまな反応が入り混じるものです。
昔から「時薬」とか「日にちが薬」と、時間が経てば乗り越えられるようなことを言う人もいますが、必ずしも時が経てば回復するというものでもありません。
普段は忘れているのに、ふと亡き人のことを思い出して身体や心の調子が悪くなることがあります。亡くなって何年経っても、その人の命日や誕生日などが近づくと、不意に臨終の場面を思い出したり「もういないんだ」と孤独感や喪失感に苛まれて憂鬱になり、しんどくなることがあります。それはどこかおかしいわけでも病気でもなく、自然な反応です。「命日反応」や「記念日症候群」などと言われるものです。
対処方法としては、無理をしないこと、休息をとって気分転換すること、あるいは故人を偲んだり誰かに話を聴いてもらったりすることで楽になることがあります。もう一つ、私はそこに「お念仏を手向ける」ことを加えることをお勧めしています。
亡き方のためにとなえるお念仏というのは、大切な方に今でも私たちができることです。日々の暮らしで亡き方のことを思い出すたび手を合わせてお念仏を手向ける。このお念仏を続けていくことで、私たちの中に積み重なっていくもの…それは、阿弥陀さまからのお慈悲をいただくことです。
最初に記した方は、大切な人を亡くして5年が過ぎています。毎年反応が出ていますが、そのたびにお念仏を手向けていらっしゃいます。
時を経ても寂しさや悲しさはやってきますが、それでいいのです。命日が近づくと反応が起こることを知っていれば、いざ反応が出ても軽く済みます。加えてお念仏を重ねれば、さらに軽くなるでしょう。まだの方も今からお念仏で備えておきましょう。
(広島県広島市 妙慶院 加用雅信)
仏縁を継ぐ夏休み 8月
During Obon, pass along to children what we have received from our ancestors.
長い間入院生活を送っていた父が 令和元年に往生しました。面会に行くたびに、弱っていく姿に辛さを感じる日々。亡くなる三日前、面会に行った時も、酸素マスク姿、かすれた声で「大丈夫か?」と尋ねてきました。自分が大変にもかかわらず、私を心配してくれていたのです。その時、どんなに辛くても私を気にかけてくれる父の姿が、私たちに寄り添ってくださる阿弥陀さまと重なるように感じました。
仏教では仏教では、何かをきっかけに仏さまを感じたり、仏教に触れることを、「仏縁」と言います。
そして、中国唐時代の高僧・善導大師は阿弥陀仏と念仏をとなえる私たちとの間には、親縁、近縁、増上縁の三種の縁「三縁」があると示されました。
親縁とは、私たちが阿弥陀仏の名をとなえるとき、仏さまはそれをお聞きになり、仏さまを礼拝するとき、仏さまはそれをご覧になる。仏さまを思えば、仏さまも私たちを思ってくださる、というもので、法然上人は、「仏も衆生もおや子のごとくなるゆえに、親縁となづく」と私たちと仏さまの間に結ばれる「親しい」関係を親子に例えました。阿弥陀さまは、まるで親のように、私たちが安らかに過ごせるようお護りになってくださっているのです。
近縁とは、私たちがお念仏をとなえ仏さまを見たいと願うとき、仏さまはその声に応じて目の前に現れてくださることを言います。実際に目に見ることはなかなかできませんが、どこにいても、阿弥陀さまは近くに来てくださり安心感を与えてくださるのです。
増上縁とは、お念仏をとなえると仏さまが念仏者の罪を滅してくださることを意味します。これは、罪をなかったことにするのではなく、その罪によ って受ける報いを、阿弥陀さまが働かないようにしてくださるということです。そして、私たちがこの世を去るときには、阿弥陀さまと菩薩さまたちが迎えに来てくださり、浄土往生をかなえてくださるとされています。
阿弥陀さまと私たちを繋ぐのは、「南無阿弥陀仏」のお念仏。
普段は忙しい生活を送っている私たちですが、お盆や夏休みで親戚や小さい子どもと集まる人もいるでしょう。この機会にともにお念仏をおとなえし、若い世代、仏教と縁がなかった方々に仏縁を継いでまいりましょう。
(三重県伊賀市 專念寺 宮嵜美政)
守られて導かれて救われて 7月
As we practice Nenbutsu, we are protected,guided, and saved by Amida Buddha.
針とお灸で逆子が改善すると聞いたら皆さまはどう感じるでしょうか。腰痛持ちの私が通う鍼灸院には、逆子を改善することで有名な先生がいます。
先生によると、人間には「経絡」という目には見えない糸のようなものが全身に張り巡らされているそうです。そして足の小指に「至陰」というツボがあり、そのツボが経絡を通じて子宮へと繋がっていて、温めたり針で刺激することによって、子宮が動いて運が良ければ逆子が戻るという理屈だそうです。
わが家の長女もまさにその施術により逆子が元に戻りました。先生は私が僧侶であると告げると次のようなお話をしてくださいました。
「『経絡』というものは科学的には未だすべて解明されておらず、すべてが解明されればノーベル賞は確実と言われるほどです。しかし、東洋医学では、はるか昔からその肉眼ではわからない『経絡』を理解し、治療を重ねてきたのです。お寺さんと私は、目には見えない、科学では完全に証明されていない、しかし確実に存在する『経絡』と、『仏さま』と向き合うという点で共通点がありますね」
ありがたいことをおっしゃるこの人は何者かと思いましたが、後にその先生は同じ市内の浄土宗のお寺の檀信徒であり、五重相伝を受けられた念仏者と聞いて大いに納得しました。
自分自身の至らなさや愚かさを見つめるとき、人の力をはるかに超越した阿弥陀さまの慈悲の心を信じずにはいられません。たとえ目には見えず、科学的に証明されていなくても、阿弥陀さまは念仏者にいつも親しく寄り添い、過ちを繰り返す私たちを決して見捨てずに間違いなく救い取ってくださいます。また、先に往生されたご先祖さまは私たちが阿弥陀さまとご縁を結ぶように、そして恐ろしい縁にめぐり合わないように導いてくださるのです。
この季節は、お寺参りやお墓参りなど尊いご縁を感じる絶好の機会です。どうかご先祖さまに手を合わせながら、阿弥陀さまに、守られて・導かれて・救われていくわが身であること、たとえ目には見えなくても確実に存在する尊い仏縁の糸を感じていただければと存じます。
(北海道札幌市 龍雲寺 丸山孝立)
自利利他 6月
Helping others helps ourselves.
「情けは人の為ならず」とはよく耳にすることわざですが、正しい意味をご存じでしょうか。「情けや親切心は相手の為にはならない」、という意味ではなく、正しくは「人にかけた情けや親切心はめぐりめぐって自分のもとに還ってくる」という意味です。きっと皆さんもこのことばの正しい意味を知らず、様々な場面で困っている人に遭遇した際に、「助けてあげるべきかな」「教えてあげたほうがいいのかな」と迷ってしまったこともあるのではないでしょうか。
私は今年の3月末までの4年間、浄土宗の宗門校である大正大学の浄土学研究室副手を務めてました。業務は多岐にわたりますが、これから浄土宗のお坊さんを目指す学部の学生さんや、大学院で研究を頑張る学生さんのサポートをすることも仕事の一つでした。
日常的に学生さんとやり取りをする中で、しばしば「レポートや論文をどう書けばよいのか」、「調べ事があるがどのような本を探せばよいのか」、「この文のこの箇所をどう解釈すればよいのか」、など多くの質問をいただくこともありました。もちろん仕事中は他にもやらなければならないことは多くあります。また、勤務時間外にも問い合わせが来ることもありました。しかし彼らは困っているので放っておくこともできません。
私は可能な限り対応することに努めました。すでに知っている、分かっていることであれば、彼らに教える中で自身の復習にもなる。そして、分からないことであれば、一緒に悩み、調べていくうちに解決の糸口が見いだせ、新たな知識や経験として自分に蓄えられていく。そのような思いで仕事をしていました。
私たちが普段おとなえするお念仏にも共通する部分があると思います。おとなえする南無阿弥陀仏の一声一声には、先立たれた大事な方に向けたご供養の想いが込められていますが、本来のお念仏とは、自分が極楽浄土に往生するためにとなえるものですので、大切な方へとなえたものも、自身の善行の積み重ねとなります。
どのようなことであれ、誰かのために小さなことから一つ何かしてみませんか。きっと私たちを成長させてくれるよい糧ともなることでしょう。
(埼玉県松伏町 源光寺 里見奎周)
完璧でないから つながれる 5月
We can connect with one another precisely because none of us are perfect.
人類は長きにわたり科学技術や文明を発展させ、より良い生活や社会の構築を目指してきました。
その一方で、私たちの世界は天災や疫病、戦争といった災禍を幾度となく経験してきました。そして、そのたびに人間の有限さ(限界があること)や未熟さを痛感させられてきました。繰り返される苦しみや悲しみを目の当たりにした時、私たちは希望を失い、時には生きる気力さえ失ってしまうこともあります。
日本の仏教において、誰よりも人間の有限さや未熟さと向き合ったのが、浄土宗を開かれた法然上人です。
法然上人は9歳にしてお父さまを非業の死で亡くされ、15歳で仏教を学ぶため比叡山に登られました。そこでの約30年間に渡る修学の中で、全ての経典を5度にわたり読破され、「智慧第一の法然房(最も智慧のあるお方)」と評されるほど学問を究められました。
そんな法然上人ですが、自身は、戒律の一つも満足に守ることができず、心を静める修行を一度も満足に行うことができず、正しい智慧を体得することなどできない存在であると述懐され、「悲しきかな、悲しきかな。いかがせん、いかがせん」と自身のお姿を嘆かれました。
完璧でないどころか、何一つ満足に物事を成し遂げることができないのが私たち人間の本当の姿なのかもしれません。それでも人類は人間の有限さや弱さを痛感し、それを受け止めたからこそ前に進むことができました。
法然上人は嘆き悲しみながら経典と向き合った末に、人間は誰もが完璧ではなく、この世では自分の力でさとることなど難しい存在であると確信されました。だからこそ、「南無阿弥陀仏」とおとなえすれば阿弥陀さまのお慈悲により誰もが等しく救われるお念仏の教えにより、浄土宗を開かれたのです。
私たちが法然上人ほどの偉業を成すことは難しいかもしれません。それでも、自身の至らなさや人間の有限さを認識することは、他者の存在の大切さを知ることにつながります。
他者を尊重し、多様な存在や在り方を認める寛容さや優しさは、ひいては人々がつながり、支えあって生きていくことのできる社会、そしてそれを認めあえる世界を創っていくことにつながるのではないでしょうか。
(愛知県知立市 了運寺 近藤修正)
呼ぶ喜び 呼ばれる嬉しさ 4月
Talking to someone for the first time takes courage, but can also be the beginning of a good relationship.
皆さんの春の楽しみは何でしょうか。ある時テレビで、桜の開花予報に従って日本列島を南から北へと車中泊で移動して楽しんでおられる方が取り上げられていました。
話の中でその方は、「桜もそれぞれ。小さい桜もあれば大きな桜もある。でも同じ桜であることに違いはない」と話されました。振り返ってみると2020年の春から数年、私たちは桜見物すらままならず、家に籠り、未知のウイルスに怯える日々を送っていました。この〝まさかの事態〟に世の無常を実感したと言えるかもしれません。その後も世界では、戦争や天災地変が続くなか、あるお医者さまが、不安定な世を生きていくことに対して「心に拠り所がある人はいつもしなやかだ」と言われたそうです。この「しなやか」は少々のことではぶれない心のふり幅と生命力ということだそうです。
仏教の教えに「所縁(サンスクリット語:アーランバーナ)」ということばがあります。所縁とはすがりつくもの、拠り所とするものを表しています。それがないと心の姿が決まらない、しなやかに生きていくことができない、そのようなものです。宗祖法然上人が北条政子の念仏往生についての質問へ答えた書簡のなかで「ただ浄土を心にかくれば、心浄の行法にて候なり」と語られています。これは、心の所縁であるお浄土を拠り所とし、お念仏の行を励むことで、阿弥陀さまのお浄土への往生がより確実なものになるということです。「南無阿弥陀仏」と阿弥陀さまの名を呼ぶことができることは、この世での大きな喜び。それが誰の声であろうと聞いてくださり、一人も漏らさずお浄土へ迎えとっていただけるという嬉しさ、それは、私たち念仏者にとって何にもかえがたい無上なものといえましょう。
冒頭の桜の話と同じように、私たちの人生のあり様もさまざまです。しかし、その一人一人が阿弥陀さまを頼み信じてお念仏して生きていくならば、愚かな私たちであっても阿弥陀さまは大慈大悲のこころで救い取ってくださるに違いありません。たとえ行き詰まることがあっても念仏者には拠り所がある、たとえ苦労、苦痛が起きたとしてもなお心を満たす大きな安らぎがあるのです。
(福岡県鞍手町 円宗寺 福田至誓)
香勲にあの人を想う 3月
With scents of spring at Ohigan(equinox), let us turn our thoughts to the loved ones in the Pure Land.
先日、日本の香水市場が拡大中という新聞記事を読みました。香水はただのフレグランスというだけではなく、その人の印象を決めるアイテムとして、また個性を表現する手段として人気が高まっているそうです。「香薫(香り)」は記憶と結びつきやすいと言われていますが、これもその一端かもしれません。私にも香りにまつわる一つの思い出があります。
お寺で育った私は、幼いころよく祖父の境内掃除の手伝いをしていました。祖父は口数が少なく、黙々と作業を進める性格でしたので、掃除の時間はおしゃべりしながらの楽しいひととき、という雰囲気ではなく、祖父の後を追いかけながらその真似をし、草取りに没頭していたことを憶えています。そしてそんな時の境内には、風に乗ってお線香の香りが漂っていました。何げないひとときでしたが、不思議と心が落ち着く、満ち足りた時間でもありました。その香りは、私にとって祖父との思い出そのものでした。
祖父は私が小学校5年生の時、72才で亡くなりました。初めて経験する、家族との死別でした。「死んだらどこに行くのだろう?」と、横たわる大好きな祖父を見つめながら悲しみに覆われ、どうしようもない気持ちになったことを憶えています。
最近、ふとあらためて、本堂に飾られた祖父の遺影を眺める機会がありました。その眼差しの奥には、生前と変わらない優しさが感じられました。祖父がもしここに居たら、自分と同じ僧侶となった私の姿を見て、「どんな言葉をかけてくれるだろう?」と考えました。「よくやっているね」と微笑んでくれるでしょうか。それとも「自分を見失わないように」と厳しく諭してくれるでしょうか。
その後、本堂で勤行をしていると、漂う香りを感じました。その香りは空気に溶け込みながらも確かな存在感を示していました。私は祖父がそばにいて、寄り添ってくれていると感じました。一緒に過ごした時間が走馬灯のように思い出され「あー、つながっているんだなぁ」そんなことを思った途端に、涙があふれてきました。
時に「香り」は、時間や場所を超えて人の心を揺さぶり、大切なことを思い出させてくれます。あなたにもそんな「香り」の記憶はありますか?
(静岡県三島市 蓮馨寺 掬池友絢)
ほのかな光で 花は開く 2月
A flower will bloom even with the faintest of light.
東京のお寺のご老僧にこのようなお話を聞いたことがあります。
第二次世界大戦終戦後、疎開先から東京に帰ってくると一面が焼け野原になっており、住まいでもあり、何百年もの歴史があったお寺も燃えてしまい、遊びに行った近所の友だちの家や、よくおつかいで行った八百屋さんもすべて燃えてなくなり、子どもながらに絶望したそうです。
しかし、瓦礫の下からご本尊の阿弥陀如来像が無事に出てきた瞬間に希望を感じ、お寺は復興できるし、この国も大丈夫だと思ったそうです。その日から気持ちも新たに阿弥陀さまを信じ、お念仏をおとなえし続けたところ、その阿弥陀さまは、やがてお檀家さまや近所の信仰のよりどころである希望の光となり、お寺も復興していったとおしゃっていました。
戦後80年、私たちの生きる現代も大変な時代を迎えようとしています。世界に目を向ければ、戦争や紛争が各地で起こり、罪のないおびただしい数の人々の命が失われています。日本でも信じられないような凶悪事件が起きていますし、天災地変など、いつ何が起こっても不思議ではありません。
法然上人は「平生の時、照らし始めて最後まで捨て給うなり」とお示しになられました。これは、苦しみの世界を生きる私たちも、常日ごろ、心の底から阿弥陀さまを信じて、「南無阿弥陀仏」とおとなえすれば、最期を迎える時も、阿弥陀さまは私たちを見捨てず、必ず西方極楽浄土にお救いくださるということ。阿弥陀さまが照らしてくださる慈悲の光は、かつてご老僧が焼け野原でご本尊の阿弥陀さまから感じられたような希望の光と同じものといえましょう。
また、できるだけやわらかな顔で優しい言葉で相手に接するというような、日々の生活での小さな善行。こうした小さな善行がやがて他の人に良い影響を与え、大変な時代、迷いの世界を少しでも良い世界に変えていくきっかけになるかもしれません。
ほのかな光ともいえる日常の小さな善行。それを積み重ねていくことが、希望への確かな光となり、いつかは花を咲かせることになるでしょう。日々、阿弥陀さまを信じお念仏をおとなえし、毎日をできるだけ「明るく、正しく、仲良く」過ごしていきましょう。
(長野市元善町 浄願坊 若麻績大成)
新たな芽の出る年に 2025年1月
This is the year to take another step forward.
一年の計は元旦にあり。一日の積み重ねが一年となり、その一年が人生を形作ります。その区切りとなる元旦に、志高く目標を立てることが大切だと昔から伝えられてきました。
しかしどうでしょうか。自分との約束を何度も破り、計画倒れになってしまう。私たちは毎年目標を立てても、日々の誘惑や慣れた生活に流されがちです。
私は、大学生の時に花粉症を発症し、以来毎年のように鼻水が止まらず、目は痒くてたまらない状態が続いています。その症状が風邪を引き起こし、体調を崩すこともしばしば。症状が出る前に薬を服用すれば軽症で済むと聞き、来年こそは花粉が飛ぶ前に対処しようと決心するのですが、翌年にはまた忘れてしまい、症状が出てから「ああ、心に決めたのに」と後悔することになります。花粉症なら笑い話で済みますが私たちの生と死の問題ではどうでしょうか。いつ命を終えるか分からない儚い私たちが死後どこに行くのか定めていたのに、計画倒れしてしまうことは大変恐ろしいことと思いませんか。
法然上人は在家信者の質問に答えた「十二箇条問答」のなかで、「念仏して往生せんと心ざして念仏を行ずるに、凡夫なるがゆえに貪瞋の煩悩おこるといえども、念仏往生の約束をひるがえさざれば、かならず往生するなり」と述べられました。
それぞれの事情でお念仏を絶え間なくとなえることができない私たちは、阿弥陀さまの願いを守れず、計画倒れになってしまいがちです。しかし、さまざまな煩悩が湧き上がってしまう凡夫の私たちでも、阿弥陀さまの救いを信じ、お念仏をとなえ続ける念仏往生の約束(決意)をひるがえさなければ、必ず阿弥陀さまは救ってくださるのだとお示しくださったのです。
私たちの一年の目標は、立てたその瞬間だけでなく、途中で何度も自らを励ましながら、自分との約束をひるがえさないように、改めて進むことが大切です。私たちの生と死の問題も、ふと極楽へ往生したいと思った時だけでなく、お念仏をとなえながら何度も自らを励まし、阿弥陀さまとの約束を守るために、あらためて進むことが大切です。それが凡夫の私たちが「新たな芽の出る年に」できる鍵ではないでしょうか。
(大分県佐伯市 潮谷寺 黒木祐)