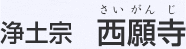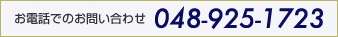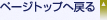周りを照らす人になろう 7月
Be someone who helps others.
長く続いた梅雨の空。夏を目前に控え、澄んだ夜空に星々が光り輝くのを心待ちにしている方も多いことでしょう。
皆さまは国際宇宙ステーション(ISS)にある日本実験棟「きぼう」をご存知でしょうか。 ISS/ 「きぼう」は、夜空に輝く星たちと同じくらいの明るさで観測ができる、サッカーコート程もある巨大な実験施設のことで、地上からはるか400キロメートル上空を1周約90分というスピードで周回し、宇宙開発技術の進展のみならず、教育や文化などさまざまな分野で貢献しています。
そんなISSを肉眼で見ることのできる条件は大きく三つ。①空が晴れていること。②近くをISSが通過すること。③地上は夜だけど、ISSは昼であること。
①と②については説明せずとも理解しやすいでしょう。では③について、そもそもISSは自らが光を放つのではなく、太陽の光を反射しているために光って見えます。ですから、ISSを地上から見るためには、ISSに太陽の光が当たっている時間、つまりISSにとって昼である必要があります。
その一方で、地上では昼間に星が見えないように、夜にしかISSの輝きは見ることができません。地上は夜だけど、ISSは昼であるという都合のいい条件はあるのでしょうか。
それは、日の出前や日の入り後の約2時間。この時間帯だけ地上は夜なのに、はるか上空のISSはまだ昼の時間になるのです。この時に夜空を見上げると、夜空に輝くISSの「きぼうの光」を見ることができるのです。
このきぼうの光は、まさに未来を照らす灯として、夢と希望を与え続けてくれます。では、私たちも周りを照らす灯となるためには、どうすればよいのでしょうか。
難しいことはありません。人々に手を差し伸べ、慈しみの心を持って接することです。大切な方が悲しんでいれば一緒に悲しみ、笑顔にしてあげたいと思う。私たち一人ひとりの心は小さな灯にすぎませんが、それがたくさん集まれば大きな光となります。それがきっときぼうの光のように、周りを輝き照らすものとなっていくことでしょう。
(北海道小樽市 天上寺 石上壽應)
心の中も衣替え 6月
When changing out your clothes for the season refresh your spirit as well.
紫式部を主人公とするNHK大河ドラマ『光る君へ』。女房たちの豪華な装束に目を奪われますが、髻(もとどり)まで透けて見える男たちの烏帽子(えぼし)しも涼やかです。聞けばあの「透け烏帽子」、12年前の『平清盛』制作時に、デザイナー・柘植伊佐夫(つげいさお)氏が絵に軽さを出すために考案したものなのだとか。髻は見せてはならぬものだったという史実が演出の後塵を拝したかたちです。
6月は衣替えの季節。冬物から夏物に替われば身も心も軽やかです。また夏らしい素材や色彩は周囲に涼をもたらします。「装い」にはそうした心遣いが託されているのです。しかしながら「装う」と聞くと、息子や孫になりすましたオレオレ詐欺などが真っ先に思い浮かぶ方も少なくないことでしょう。つくづく物事を好意的に受けとめることが困難な時代です。
今から23年前、私は20代後半になってから四国の寺へ帰りました。大阪での会社勤めを終えたばかりで、法衣を着るどころか、法衣に着られるような始末。そんなある日、出先から法衣姿で帰ったところ一人のご婦人と邂逅しました。かつて併設していた保育園で長年にわたって保育士として勤めてくださった先生でした。私にもずいぶん手を焼かれたはずで、このバツの悪さをどうごまかしたものかと、必死で言葉を探し、自身を装いました。ところが先生は私をひと目見るや、合掌されて深々と頭をお下げになられたのです。慌てて私も合掌しましたが、先生の嬉しそうなお顔を拝見すると、ますます言葉は見つかりませんでした。
「水を掬(きく)すれば月手に在り花を弄(ろう)すれば香衣(こうえ)に満つ」。唐の詩人・干良史(うりょうし) の句です。水を掬(すく)えば掌(てのひら)に月があり、花を折れば香りが衣に移る。『光る君へ』では紫式部が桶の水に映る月に道長を重ねて両手で掬うシーンが印象的でした。
葦の生い茂る池にも月は宿ります。遠くからは分からなくとも、近づいてよく見れば葦の奥から顔を覗かせる月影(つきかげ)。お念仏をとなえていれば、妄念の葦が茂っていようとも、暗夜を照らす阿弥陀さまの光明をしっかり頂戴することができると、法然上人はお示しくださいました。どんなに心が覚束(おぼつか)なくとも怠らず努め励む。すると自然に心が具そなわっていくのです。
(愛媛県愛南町 金光寺 吉田哲朗)
比べなくても あなたはあなた 5月
You have your own good qualities so don't compare yourself with others.Just be who you are.
新緑が目に鮮やかな季節になりました。私はスギの花粉症なので、久々に新鮮な空気を思い切り吸い込めてうれしい毎日です。お檀家さんに会えば、「良い季節になりましたね」とあいさつを交わしています。
しかし、ふと考えてしまいます。本当に良い季節なのかしら、と。私にとっては良い季節でも、イネの花粉症の方にとってはピークを迎える悪い季節かもしれません。「良い」も「悪い」も人それぞれに異なるもの。「季節」はただ「季節」に過ぎず、私たちが勝手に個人的評価をつけているだけなのかもしれません。
私たち自身も勝手な評価をお互いにつけ合い、時にそれに苦しんでいると感じることが多々あります。職業柄、悩みの相談を受ける機会がありますが、そこで気づくのは評価されたり、比べられたりすることに疲れている方々がたくさんいるということ。この世界は小さいころから、成績という評価軸で他人と比べられる競争社会です。例えば95点をとっても、親からはほめてもらえずに、「なんでこの5点ができないんだ!」と叱られていたなんてお話をうかがったことがあります。その親にとっては「95点を取ったがんばった」子ではなく、「あと5点を取れなかった残念な」子になってしまい、本人もご自分をそう思うようになってしまったのだそうです。
家庭や学校では「良い子」や「普通の子」であることを求められ、ちょっと外れてしまうと「ダメな奴」「変な子」というレッテルを貼られてしまう。大人になっても同様で、いつまでも他者からの評価を気にする社会に生きなければなりません。疲れてしまうのも自然なことです。
浄土宗が拠り所とする経典『阿弥陀経』に、「青色青光 黄色黄光 赤色赤光 白色白光」という一節があります。これは極楽浄土では青い花は青い光を、黄色い花は黄色い光を放つという描写で、それぞれの花がそれぞれの光で輝く、その良さを示したものです。
阿弥陀さまの世界は、評価されることも比べられることもなく、みんながそのままでいて良い世界。現代社会はなかなかそうはいきませんが、阿弥陀さまはいつも、「あなたはあなたのままでいいんだよ」と語りかけてくれています。
(東京都府中市 蓮宝寺 小川有閑)
開宗の文(法然上人が浄土宗を開くきっかけとなった要文) 4月
Let us practice nembutu wholeheartedly.Namu Amida Butsu.
皆さん。読書は好きですか。私は大好きです。時間を見つけてはなにかしらを常に読んでいます。本は自分が見たこともない世界や物語を体験させてくれます。見たこともない異国の情景や文化、手に汗握る冒険の世界、涙無しには読めない悲恋の世界、故人の深淵な哲学思想などなど、本さえあれば部屋から一歩も出ずにどんな世界にも遊びに行くことができます。そして本を介したそれらの世界での体験は自分の糧となります。本の力は絶大です。皆さんも人生を変えた一冊が何かあるのではないでしょうか。
法然上人にも人生を変えた一つの書物との出会いがあります。それは、中国唐代の高僧・善導大師の『観経疏』です。当時の仏教では、救われるためには難しい修行や厳しい条件が必要であるという見解が一般的でした。そこで、法然上人は誰もが平等に簡易に救われる教えを求め、比叡山黒谷の青龍寺で毎日、一切経とよばれる仏教の経典や論書を紐解いていました。そのような中、出会われたのが、今月のことばである「一心専念弥陀名号(一心に専ら弥陀仏の名号を念ず)」に始まる善導大師の『観経疏』の一節です。平易に言い換えれば、「往生できると信じて(一心)、ひたすら(専)、阿弥陀仏の名号をおとなえする(念弥陀名号)」となります。法然上人はこの『観経疏』の一節との出会いをきっかけに、「誰であったとしても、往生極楽を願って南無阿弥陀仏とひたすらとなえるだけで、極楽に往生することができる」という浄土宗をお開きになりました。その後、お念仏の教えは法然上人の人生を変えた様に、多くの人々の人生を変え、全国に広まり、時代を経ても変わることなく継承され、今なお我々に生きる力を与え続けています。
ちょうど今年は法然上人が『観経疏』の一節とお出会いになってから850年目と、節目の年になりました。はるか昔の『観経疏』との出会いが、上人の人生を変え、そして後の世に生きている我々の人生を変えたのです。我々の支えとなっているお念仏の教えは、上人と一冊の書物の出会いがきっかけだったのです。
一冊の本との出会いが人ひとりの人生を変えるように、お念仏の教えとの出会いが皆さまの人生をより良いものに変えることを願っています。
(滋賀県大津市 西方寺 田中裕成)
未来を信じ 今日を励む 3月
Whether things are going well or not, try your best right now and have trust in the future.
第58代横綱千代の富士。「ウルフ」の愛称の通り、精悍な顔つきに筋骨隆々とした肉体美を持ち、少年時代の私をテレビに釘付けにした、昭和から平成にかけて活躍された力士です。
優勝回数や通算勝ち星等々、輝かしい成績を残し、記録にも記憶にも残る大横綱。しかしその土俵人生は順風満帆なものではありませんでした。
千代の富士は入門当初、力士の中では体格に恵まれていませんでしたが、身体能力が高く、力が人一倍強かったため、強引な相撲が目立っていました。しかしそれが仇となり、度重なる怪我に悩まされます。特に幾度となく襲った肩の脱臼は深刻で、力士生命を脅かすものでした。
引退も頭をよぎる中、一つの決意を固めます。それは毎日500回の腕立て伏せを欠かさずやるというものでした。これは肩の周りの筋肉を鍛え、怪我を予防また克服するためのものです。今日の一つ一つの積み重ねが、自らの未来へと必ず実を結ぶと信じて励まれたのだと思います。もちろん毎日500回の腕立て伏せというものは、千代の富士の努力の中の一つに過ぎません。しかしこれが、強靭な精神力と肉体を作り上げ、大横綱へとなっていく礎となったことはいうまでもありません。
私たちの日常においても同じことが言えます。仕事や学問、趣味の分野など様々な事柄の中で、今日の一日を励み、そしてその一日をしっかり積み重ねていく。順調なときもあれば、うまくいかないときもありますが、しっかりと日々を歩むことが、自らを豊かにし、必ず実を結んでいくはずです。
お念仏の信仰において宗祖法然上人は、「一紙小消息」というお手紙の中で、「行は一念十念なお虚しからずと信じて、無間に修すべし」とお示しくださいました。これは一声や十声のお念仏であっても必ず往生の実を結ぶと信じて、日々おとなえしなさいとのお示しであります。お念仏をおとなえしていく日々を重ねていくことで、私たちの心は豊かになり、命終(現世で命尽きるとき)には必ず極楽浄土へ往生を得ることができるのです。
人生山あり谷あり。平坦な道ばかりではありませんが、自分や目標を見失うことなく、お念仏の信仰も生活の中の様々な事柄も、その日々の歩みをしっかりと進めていきたいものです。
(熊本県熊本市 往生院 永目眞爾)
日々の合掌 心の手当て 2月
Thinking of those who have passed and putting your hands together each day can bring you peace of mind.
ある新聞の記事で、「あなたは今、幸せですか?」という質問に対して「はい」と答える方の割合は50代前半が最も低く、年齢が上がるほど高くなる傾向にあるという、アンケート結果を目にしました。90歳を超えるとその割合が急激に増え、90歳以上の8割の方が「今、幸せです」と答えていました。
その理由を見ると、身体的な機能は低下しても今できることや周りの人への感謝、老いた自身をありのまま受け入れる心の余裕から幸福感が増すという内容でした。現在、50代前半の私は、この記事を読み、将来がとても楽しみになったと同時に、法然上人が常におっしゃられていた、あるお言葉を思い出しました。
「生けらば念仏の功つもり、死なば浄土へ参りなん。とてもかくても、此の身には、思いわずろう事ぞなきと思いぬれば、死生ともにわずらいなし」。これは、生きている間は、日々お念仏をとなえ、阿弥陀仏に全てをお任せすることで、いつ命が尽きても、阿弥陀仏の救いによって極楽浄土へ必ず往生でき、この世の悩みや苦しいことも思いわずらうことなく、死を迎えることすら穏やかに受け入れられる、とのお示しです。上人は43歳で浄土宗を開宗し80歳で往生されるまで、波乱万丈の日々の中でも、この御心で毎日六万遍のお念仏をとなえ、思いわずらうことなく力強くこの世を生き抜かれたことがお言葉から伝わります。
上人のように日々六万遍もお念仏をとなえることは私には出来ませんが、コロナ禍となった4年前からそれまでは日課としていた朝の勤行を、夕方にも行うようになり、現在まで続いています。となえるお念仏は朝夕合わせて、上人の百分の一の六百遍程度でしょうか。それでも自分ではよく続いていると思うところですが、正直にいうと日々お念仏をとなえながらも、心の中はいつも思いわずらうことばかりです。
この先、日々念仏をとなえ続けることで、上人がお示しの通りの「死生ともにわずらいなし」の境地に至るのか、その前に命尽きるのか、はたまた90歳を迎え幸せを感じる毎日を迎えるのかは分かりませんが、極楽浄土へ往生することが間違いないお念仏の教えに出会えたことに幸せを感じ、ただ一向に「南無阿弥陀仏」をとなえる日々です。
(青森県青森市 正覺寺 楠美知剛)
一人ひとつの積み重ね 1月
Do what you can now,and build on that one by one.
2024年、新たな年を迎えました。みなさまはどのような年を迎えましたでしょうか。家族とともに温かく迎えた新年でしょうか。新たな目標に向かう希望に溢れる新年でしょうか。
来し方を振り返ると、さまざまなことが思い浮かびます。いまは随分と落ち着きましたが、2019年に発生し世界中で猛威を奮った新型コロナウイルスは、多くの人々の命を奪って、私たちの生活を変えてしまいました。2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は現在でも終わりを見せる気配もなく、悲しみや怒り、恐怖のうちに生活する人々がいます。さらに昨年10月には、イスラエルとハマスの戦闘が起き、やはり多くの人々が命を失いました。この他、世界中ではまだまだ不安の中に生きている人々がいます。
浄土宗に関係するところでは、昨年8月、ハワイ・マウイ島での山火事があげられます。この火災では、現在97名の死亡が確認されており、31名がいまだ行方不明となっています。そして同島にあるわが宗のラハイナ浄土院は全焼し、この日本から遠く離れた場所で、私たちと同じようにお念仏する人々の心の拠り所が失われました。
「一人ひとつの積み重ね」
世界情勢の変化やわが国の経済の衰退により、物価は高騰し収入は減少しています。私たちの生活も楽ではないものに変化していっています。このようなときですので、一人ひとりが大きなことはできません。しかしながら、一人ひとりのほんの少しが積み重なれば、失われた心の拠り所を取り戻すことができます。
宗祖・法然上人は次のように説いています。
「同じ心で極楽を願い念仏を申す人は、たとえ遥かに遠く離れた国の人であっても、同じ志で仏道を行う仲間であるという思いを懐いて、同じ阿弥陀仏の浄土に生まれようと思うべきである」(津戸三郎入道へ遣わすお返事)
さて、本年は浄土宗開宗850年の記念の年です。この年に、世界中の多くの問題を解決することはできなくとも、まずは遠い海の向こうの地の、私たちと信仰を同じくする仲間の心の拠り所が復興されることは、宗祖のご恩に報いることになるのではないでしょうか。
(愛知県豊橋市 太蓮寺 市川定敬)
希望の灯 どこまでも 12月
Good deeds you have done for others are certain to help you.
本年も残すところあと僅かとなりました。年末になると、この一年や人生を振り返る方も多いかと思います。みなさまはこれまでどのような人生を歩んでこられましたか。幸せなことがあれば反対に辛いこともあるのが人生というもの。山があり、谷があり、そして「まさか」という坂があるともいいます。いつ何が起こり、苦しみ、悩み、迷ってしまうかわかりません。人生という名の荒波の航海を続けるには導きとなる目標が必要ではないでしょうか。
岩手県大槌町には人形劇『ひょっこりひょうたん島』のモデルともいわれる蓬莱島というひょうたん型のとても小さな島があります。この島には古くから灯台が立っていましたが、東日本大震災による津波で倒壊してしまいました。そこで、復興のシンボルとして親しんでもらえるよう公募で選ばれたデザインをもとに、震災翌年の12月に灯台が再建されました。新しい灯台は赤蝋燭と砂時計の二つをコンセプトとした形で、頂きの光る部分は太陽を表し、それらは、「鎮魂の祈り」と「復興に向けて時を刻んでいくこと」を意味しているそうです。まさに、町の人々をどこまでも照らし続け、未来へと導いてくれる「希望の灯」といえるものです。
そして、この町では「希望の灯」の導きとともに、蓬莱島から正午になると人形劇『ひょっこりひょうたん島』の曲が鳴り響き、人々を勇気づけているのです。そのようにして、復興に向けて一日一日、一歩一歩、確かに歩んでいる人々の姿に私自身とても大きな勇気を与えられたのでした。
「苦しいこともあるだろさ 悲しいこともあるだろさ だけど僕らはくじけない 泣くのはいやだ 笑っちゃおう 進め!」(「ひょっこりひょうたん島」 歌:前川陽子、作詞:井上ひさし・山元譲久、作曲:宇野誠一郎)
法然上人は苦しみや悲しみに暮れる人々に心から寄り添い、お念仏のみ教えをお示しくださいました。そのみ教えはまさに私たちの未来をどこまでも照らし導いてくださる「希望の灯」です。私たちはその灯を自己のよるべとして、「南無阿弥陀仏」とお念仏の声を響かせながら、この人生を確かに歩ませていただきたいものです。
(京都府伏見区 阿弥陀寺 岩井正道)
今さらでなく 今から 11月
The moment when you make a resolution is the perfect time to start fulfilling it.
コロナ、WBC、大谷翔平。豪雨、猛暑、台風、大谷翔平…気がつけば今年も既に11月。時間が過ぎるのは本当に早いものです。
今年の1月に、日本列島を襲った大寒波は本州西端の私の住む町にも大雪を降らせ、我が家の水道管も何十年かぶりに破裂しました。夜遅くになって「シャーシャー」と水の噴き出す音に気づき、慌てて外へ元栓を閉めにいきました。これが刻一刻と過ぎていく人生の時間の流れであれば、音もしませんし止めておく元栓もありません。ボーッとしていようと、落ち込んでいようと、時間は待ってはくれません。
人生百年時代とはいえ、一人の人間が一生の間に出来ることには限りがあります。今、本当にやりたいと思うことや、やっておかなければいけないと感じることがあるのであれば、先延ばしせずにすぐ始めることです。「やらなければいけない」とか「どうしてもやりたい」という気持ちが心に生まれるのは、「やりなさい」「始めなさい」という知らせのような気がします。自分の心に響いてくる内なる声を信じ、一度きりの人生、機を逃さないようにしたいと思います。
早いもので、私も住職に就任して30年が過ぎました。就任してまだ間もない頃、現役で仕事されていたお檀家さんに「仕事を辞めたらお寺参りさせてもらいますから」とよく言われてました。あれから30年。一度もお寺参りされることなく、その方は旅立っていかれました。あの時どうしてもっと強く「時間ができてからでは遅いですよ。時間は自分で作り出さなきゃいつまでたってもお寺参りはできませんよ」と言えなかったことが悔やまれます。
「いつまでもあると思うな親と金」子どもの頃よく聞かされた言葉ですが、今や親やお金の心配よりも「いつまでもあると思うな我が命」と、いつの間にか自分のことを心配しなければいけない年齢になっていました。年齢に関係なく、もっと早く気づけばよかったのでしょうが、生きている限り遅過ぎるということはありません。人として与えられた時間に限りあることに気づき、そのことときちんと向き合い始めた時から本当の人生が始まるのではないでしょうか。日々お念仏を申し、阿弥陀さまのお迎えがあるその日まで、一日一日を精一杯生きましょう。
(山口県山陽小野田市 大福寺 神田大聖)
的が決まれば あとは射るだけ 10月
Constantly chant the name of the Amida Buddha to attain birth the Pure Land.
大谷翔平選手は、私の地元である岩手県奥州市の出身です。私は大谷選手と同じ中学です。実家も近所なので大谷フィーバーの最前線のような場所にお寺があります。侍ジャパンの世界一など、活躍のたびに地元では大変な盛り上がりでした。今では日本だけでなく世界中の人々から応援される選手になったことはとてもうれしく思います。
大谷選手は、野球を始めた小学3年生の時から「プロ野球選手になる」と目標を決めました。目標達成シート(マンダラチャート)は特に有名です。①体づくり②人間性③メンタル④コントロール⑤キレ⑥スピード160キロ⑦変化球⑧運という八つの項目について詳細に検討しました。目に見える所に張り、時には書いて、常に口にしました。それを確実に、かつ継続的に実行してきた結果、前人未到ともいうべき大リーグでの二刀流の活躍に結実しているのはご存じのとおりです。
今月の標語は「的が決まればあとは射るだけ」。けれど、私たちの人生を顧みた時、目標となる的を定めているでしょうか。漠然と健康や長生き、美しいものや、おいしい食べ物を手に入れることが目標になっていないでしょうか。
今こそ大谷選手を見習い、確かな人生の目標を決める時です。浄土宗の目標は極楽往生です。阿弥陀さまは南無阿弥陀仏ととなえたものを、阿弥陀さまの住む世界である極楽浄土に救うと本願に誓われています。極楽往生を目指し、生涯南無阿弥陀仏ととなえ続ければ、臨終の後に阿弥陀さまが迎えに来てくださります。心身ともに安らかにしてもらい極楽に往生します。その後は一切の苦しみなく、成仏させていただけます。
法然上人は「一枚起請文」の中で「ただ往生極楽のためには、南無阿弥陀仏と申して、うたがいなく往生するぞと思い取りて申す外には別の仔細候わず」とお示しです。極楽往生という目標のためには、必ず往生すると信じて南無阿弥陀仏ととなえることだけが大事だと教えてくれているのです。
「的が決まればあとは射るだけ」とは、
「極楽に往生するという目標が決まれば、あとは南無阿弥陀仏ととなえるだけ」といえます。共々に念仏精進してまいりましょう。
(岩手県奥州市 真城寺 吉水晃教)