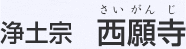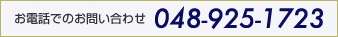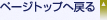水たまり ひとつ ひとつに 陽の光 6月
As it reflects in every rain puddle,the sun illuminates us all.

6月は水無月ともいいます。「水が無い月」という意味ではなく、水の月。つまり田植えに多くの水を必要とする月です。暦の上では梅雨入りとなり、農家にとっては田植えの日を決めるうえで、梅雨の時期を知ることは重要でした。気象学が発達していなかった江戸時代に、目安として暦の上で入梅を設けたそうです。
同じ「つゆ」でも「露」を、仏教では人の命にたとえます。朝露のように儚く、人の命はいつ消えてしまうかわからないもの。しかし、紫陽花の葉の上に残る一滴の朝露はたとえ儚いものだとしても、陽の光を浴びた時、何より輝き美しいものとなります。露のように儚い命も「必ず救うぞ、必ず導くぞ」とお誓いくださった阿弥陀仏の大慈悲の光明はお念仏をとなえる私たち一人ひとりに降り注ぎ、漏らすことはないのです。また、法然上人のお歌に
露の身は ここかしこにて 消えぬとも 心は同じ 花のうてなぞ
とあります。
これは露の身のように儚いお互いの身でも、後世必ず西方極楽浄土で再会できる、と詠んだものです。
小学生時代のある夏、両親から買ってもらった長靴を早く履きたくて、玄関にその新品の長靴を置いていました。雨の日を今か今かと待っていましたが、そんな時は晴れが続くもの。ようやく雨になると〝待ってました〟とばかりに長靴を履き、水たまりを駆け回っていました。雨の日が楽しかったのです。きれいな水たまり、濁った水たまり、深いものや浅いもの。雨あがりに射す陽の光で、雨水をお腹いっぱいため込んだ水たまりは、鏡のように上空の青空や周りの景色を映し出し、覗き込むと自分の顔も映ります。陽が射したおかげで、水たまりに映る自分の姿が見えるのです。
南無阿弥陀仏は「助けたまえ阿弥陀仏」という意味。もちろん、往生するためにおとなえするのですが、となえるうちに普段気付けなかった本当の自分の姿に気付けるものかもしれません。現代社会を生きるためには、自分を高く評価してもらい、他に負けない自分をつくることも必要かもしれませんが、それは本当の姿を見失わせている原因のひとつかもしれません。
気負わず、自分自身を責めず、ありのままの私を救ってくれる。梅雨の合間に射す陽の光の温かさを感じるたび、阿弥陀仏のありがたい存在を感じるのです。
(神奈川県真鶴町 西念寺 小俣慶樹)